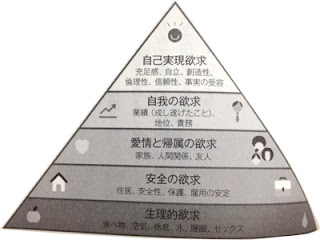)) 背伸びしないブログの続け方
人が着る服は、次の2択で決められていると思います。 1)その服がただただ好きか 2)その服を着て人にどう思われたいか このブログを書くときも、上記のどちらかがベースのネタがあって、(2)のネタを書くと、常に違和感がつきまとうわけです。 ブログを書くなら「人に読まれなきゃ。」 ブログで「セルフブランディング」 web業界では当たり前です。 上記の(1)か(2)かでいうと、(2)です。 「人に読まれるブログ」は「自分が書きたい記事」ではなく「ユーザーが読みたい記事を」というのが当然で、「ユーザーが読みたい記事」は、さらに人に共有されやすい。 だから「ユーザーが読みたい記事」を書いた方がいいんだよね・・・そんな意識を少しでも持った状態で書くと、書き終わった後に、すっきりしないんです。良い内容が書けたとしても、なんだか後味が悪いんです。 「長いこと書いてないから何か書かなくちゃ」という気持ちも、ブログをもっていれば自然です。しかし、そんなきっかけで書いた記事の内容は、上手に書けたとしても、「書きたいと思ったネタ」「自然と湧き出たネタ」ではないので、やっぱり違和感がつきまといます。 例えば、私は花を育てるのが苦手。 枯らしてしまうので育てません。 それは、「枯らしてしまうこと」を恥じていたからです。逆にいうと、「花を咲かせること」が、誰もが当然感じる”一番の魅力”なんだろうと思い込んでいたからです。 しかし考えを変えてみたら、「花を植えるために土をいじる」「花に水をあげる」「花に水をあげるので毎朝同じ時間に起きる」。花を咲かせる以外にも、花を育てるには様々な行程があって、そのどれかひとつだけでも魅力を感じるならば、花を枯らしてしまう可能性があっても、花を植えてみるべきなんだなーと。そのわずかな時間は、きっと人生を豊かにしてくれるだろうし、もしかしたら、「花に水をあげる」時間が好きなのであれば、そこから花を枯らさずにすむ方法を身に付けられるかもしれませんよね。 ブログも一緒で、人に読まれること以外にも魅力を感じる部分があるのであれば、それは人に読まれなくてもやるべきなんですよね。 私の場合は、自分が好きで気になって色々調べたり考えたりして、そこから湧き出た自分の言葉をブログにまとめることで「自分の頭が整理さ...