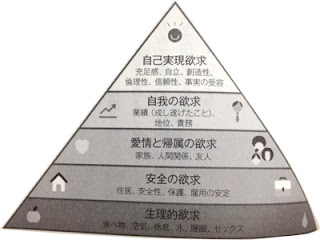)) 久しぶりに、心に響いた言葉
マーガレット・サッチャーの映画を観ていて、 久しぶりに、心に響く言葉と出会いましたので記録。 ----------------------------------------- 今の時代の問題のひとつは 人間の関心は、"どう感じるか"で ”何を考えるか”ってことじゃない ”考え”とか”アイデア”こそが面白いのに ”考え”が”言葉”になる その”言葉”が”行動”になる その”行動”がやがて”習慣”になる ”習慣”がその人の”人格”になり その”人格”がその人の”運命(さだめ)”となる ”考え”が人間を創るのです ----------------------------------------- そしてやっぱりまた思うのが、 何を”考える”べきか、”気付ける”こと。 日常を何気に過ごさないこと。(たまにはいいけど) 当たり前を、当たり前と思わないこと。(たまにはいいけど) 何かに気付いた自分を、スルーしないこと。(たまにはいいけど) そして、もっと昔から私が大事にしている言葉。 せっかくなのでそれも記録しておこう。 たとえ勝てはしないゲームでもどうにかなるの。 by ユニコーン これも、”気付き”のひとつ、 なんだよなー。